新規事業やイノベーション創出は、大変な仕事です。
新規事業やイノベーション創出は、
既存事業の進め方とは大きく異なるため、
ベテランのビジネスパーソンの方であっても、
一朝一夕にはいかないものです。
ビジネスの本質が固定的ではないのと同様に、
新規事業やイノベーション創出についても
「こうしなくてはいけない」というものはありません。
そのため、自社の強みを鑑みながら、
不確実性が高い状況のなか、市場の未決の課題を探り、
手探りで事業を進めていくことが必要となります。
このように書きますと、新規事業やイノベーションは、
各社ごとに独自の方法で
進めていかなくてはいけないと考えられるかもしれません。
確かのそうした部分も多分にあると考えます。
しかしその一方で、MOTや先進企業のケーススタディ、
新規事業担当者の方とのご相談案件を通じて、
進め方の橋頭保となるようなものがあるのではないかと考えるようになりました。
こちらのページでは
橋頭保となるような基本的な進め方について、まとめています。
■基本的な進め方
(1)「イノベーション」の本質を理解する

イノベーションとは:イノベーションは「技術革新」ではなく「新結合」
「イノベーション」という言葉を聞くと、 多くの方が「新技術」「技術革新」と連想されないでしょうか。 しかし、本来のイノベーションという言葉は「新結合」を意味します。 実は、イノベーションは「技術である」という誤解が、 長年、日本企業にとって...

「イノベーション」と「インベンション」の違いを認識する
2019年にノーベル化学賞受賞された 旭化成名誉フェローの吉野彰さんが、 2019年12月11日にストックホルムで記念講演をされました。 吉野さんはリチウムイオン電池を開発した功績により、 ノーベル賞化学賞を受賞しています。 受賞記念講演の...
(2)「市場の未決の課題」へ取り組むことの理解

「市場の未決の課題」を発見する方法:開発者が市場との接点を持つことの重要性
イノベーションや新規事業創出の際において、 「市場の未決の課題」からスタートすることは、 進め方として王道であり、事業化の成功確率も高くなります。 「市場の未決の課題」を探索するためには、市場と接点を持ち、 観察を行うことで、顧客が気づいて...

新規事業における「目利き」の力とポイント
新規事業やイノベーション創出を行う際に議論のなかで 「目利き」の力が重要ということが言われます。 目利きの力とは、 自社のシーズを見極めて、 さらに市場の課題を探索しながら、 うまくマッチングさせることができる能力を指します。 自社のシーズ...
(3)自社の強みについて改めての分析

新規事業、イノベーションにつなげる自社の強みの見つけ方
新規事業やイノベーションの創出をスタートさせる際には まず、自社の強みを把握することが必要です。 イノベーションは「新結合」です。 自社の強みと別の要素を組み合わせることで、 これまでにはない価値を生み出すということが王道的な対応となります...

「モノ売り」から「サービス化」の視点で「自社の真の価値」を知る
新規事業を検討したり、事業計画を見直す場合などで 自社の強みについて、再認識することは非常に重要です。 自社の強みについては、もちろん自社の社員の方が最もよく理解しているかと思いますが、 一方で、社内から見た場合と社外から見た場合で、 別の...
(4)経営ビジョンから開発の方向性の策定

ロードマップの作り方の基本:6つのプロセスで進める
前回は、 ロードマップの基本と活用のポイントについて述べました。 ロードマップは、未来基軸で 現在から将来への道筋を推測、計画する手法です。 また、「あるべき姿」に至るまでの道のりを 関係者の間で意識共有のツールとして活用することで、 大き...

「拡散」と「収束」の2つの段階を意識することが新規事業を成功に導く
新規事業やイノベーションについて、初期段階では、議論・検討を行い 様々なテーマやアイデア出しを行います。 しかし、議論が広がりすぎて収集がつかなくなり、 うまくテーマの絞り込みができなかった という失敗のケースもあるようです。 こうした失敗...
■各種ツールの使い方
・ロードマップの策定

ロードマップの基本と2つの活用ポイント
多くの企業で、全社方針やプロジェクトの策定、 新規事業やイノベーションを起こす際に、 ロードマップが活用されているのではないでしょうか。 ロードマップは策定することで、 現在の自社が置かれている状況、環境をどのように理解すれば良いか、 その...

ロードマップの作り方の基本:6つのプロセスで進める
前回は、 ロードマップの基本と活用のポイントについて述べました。 ロードマップは、未来基軸で 現在から将来への道筋を推測、計画する手法です。 また、「あるべき姿」に至るまでの道のりを 関係者の間で意識共有のツールとして活用することで、 大き...
・ステージゲート法の運用

ステージゲート法の進め方(1):新規事業創出を成功させるポイント
現在、多くの企業で、 新規事業創出のために「ステージゲート法」が導入されています。 「ステージゲート法」はある一定以上の規模の企業で、特に研究開発の場面で、 新規事業をマネジメントする手法としては、非常に有効で、 成果につなげている企業も多...

ステージゲート法の進め方(2):運用上の2つの課題をクリアするポイント
前回は下記の記事でステージゲート法の基本についてお伝えしました。 (まだご覧になっておられない方は、是非ご参考ください) 今回は「パート2」として、 実際に運用するなかで課題となりやすい2つの点について その解決方法を解説します。 「ステー...
・フェルミ推定

フェルミ推定によるマーケットサイズのつかみ方:いくらで売るかのヒント
新規事業やまったく新しい商品開発を進める場合、 どの程度の売上が見込めるか事業計画の立案を求められることが多いかと思います。 既存事業であれば、これまでのビジネスの進めるなかで見えてきた 大枠の価格帯、感覚があるため、それがベースとなるかと...
・市場の未決の課題を発見するには

「市場の未決の課題」を発見する方法:開発者が市場との接点を持つことの重要性
イノベーションや新規事業創出の際において、 「市場の未決の課題」からスタートすることは、 進め方として王道であり、事業化の成功確率も高くなります。 「市場の未決の課題」を探索するためには、市場と接点を持ち、 観察を行うことで、顧客が気づいて...
・オープンイノベーションの役割

新規事業、イノベーションを成功に導くオープンイノベーションの使い方
新規事業やイノベーション創出の分野で、 ここ数年「オープンイノベーション」が注目されています。 「オープンイノベーション」は、 ハーバード大学経営大学院教授ヘンリー・チェスブロウによって 2003年に提唱された概念です。 自社だけでなく他社...

オープンイノベーション施設とお勧めの見学先
現在、B2B企業の多くで、 マーケティング的な取り組みの一環として、 オープンイノベーション施設を開設しています。 オープンイノベーション施設では、 自社の製品や素材を陳列し、パネルの説明とともに それらの特徴について顧客に理解してもらい、...
・大学との共同研究

大学との共同研究を進める際の注意点:企業が課題を明示することが必要
近年、多くの企業で大学との共同研究が行われるようになりました。 経済産業省も産官学の共同研究を推進しており、 国として大学という知の集積地を有効活用し、 日本としての価値を生み出したいと考えています。 大学教授は、その道の専門家であり、 最...
■日ごろの情報収集の方法
・情報収集

新規事業、イノベーションのためのアイデア、発想のヒント
アイデア発想や気付きを発見する方法について、 世の中では、さまざまな情報や書籍が紹介されています。 「発想法」は問題解決の手法となりますが、 今回の記事は発想のヒントについて、 ユニークなものを中心に解説していきます。 異なる分野、領域の「...

「新産業構造ビジョン」「NISTEP サイエンスマップ調査」は最高峰の情報源
先日、企業の研究開発担当の方とお話しをしていると、 次のようなことを言われました。 「自社が取り組むべき課題がなかなか見えてこない。 経営者も方向性を指し示せないでいる」 確かにそうかもしれません。 かつてであれば、自社の強みを生かして、 ...
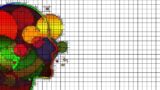
404 NOT FOUND | あなたのためのイノベーション

「知の探索」活動により、イノベーションの可能性を高める
早稲田大学ビジネススクール准教授である入山章栄先生は 現在、大きな注目を集める経営学者の一人です。 入山先生は、 イノベーションについて「新結合」であるというシュンペーターの主張に 改めて注目し、たびたび強調しています。 入山先生の指摘する...
・PEST分析

PEST分析の基本とPEST分析を通じた「気づき」の醸成
多くの企業で、マーケティングの際に、 PEST分析を活用していることと思います。 しかし、PEST分析は、マーケティングだけではなく、 新規事業やイノベーション創出の観点から、 「市場の未決の課題」を意識して、 日々続けていくと経年の変化が...
・発想法
404 NOT FOUND | あなたのためのイノベーション
■悩んだ場合
・イノベーションを起こすことの必要性

製品のコモディティ化に対抗し、高い利益率を維持するためのイノベーション
現在、アジア各国の技術的発展に伴い、 日本企業がある段階までグローバルで優位性を保っていた製品や技術について、 短期的にキャッチアップされて、コモディティ化してしまい 世界でのシェアが一気に低下してしまうという状況が起きています。 この状況...

イノベーションの必要性:「赤の女王仮説」から見える「生き残るためのイノベーション」
既存事業で安定的な成長を持続している企業の場合、 新規事業やイノベーションの経営的な重要度が低いことがあります。 新規事業やイノベーションは、 成功確率が低いため、あえて挑戦する必要はないという考えからです。 しかし、企業の持続的な存続を考...
・悩み

新規事業の仕事がツライという悩みのあるあなたに
新規事業の担当に配属されて、業務に対応されるなかで、 日々ツライという方が多くおられると思います。 そのお気持ち、よーく分かります。 私自身も新しいテーマの事業を担当して、 3年ほど全く収益の目処がつかない状況を経験しています。 事業単体と...

新規事業担当になって辛いという方に:目的意識の寓話
新規事業やイノベーションを成功させるまでの 道のりは長く、険しく、時に失敗も伴うものです。 必ず成功するという保証もなく、 事業化に成功したからといっても、 市場での大きな売上にはならず、 結果的に評価につながらない場合もあります。 このよ...
・企業事例について
下記のリンクで一覧にしていますので、ご参考ください。

イノベーションの参考になる企業事例
本ブログで紹介した事例についてまとめました。 他社事例を自社に取り込むための方法については、下記の記事に解説しています Airbnb(エアビーアンドビー)とクロネコヤマトについての対応 ウーバーが、タクシー業界に与えたインパクトと対応 老舗...
